
新入学、新学年
一つ学年が上がるこのタイミングでおもちゃの収納を見直したいママさんからご依頼をいただきお手伝いしてきました。
姉妹(小3、小1)のおもちゃ棚

リビングの一角に置いてあるこのオモチャ棚、一見ちゃんと収納されているように見えますが、それは
「使ってないからきれいなまま」とのこと。
確かに引き出しはぎゅうぎゅうに入っているから開け閉めがしにくい。
・姉妹が仲良く使えるように
・姉妹だけで出し入れできるように
・使いたいものがすぐ出せるように
・使ったものを次のために戻せるように
この5つがママと姉妹のご希望です。
ステップ1 なかのものを出して分けていきます。
・・・といってもそこはまだお子さま、すべて出してしまうとおもちゃに目移りしてしまってお片づけが進みませんので引き出し一つずつ。
今回はこんな風にわけました
1.姉のもの、妹のもの(それぞれの宝物含む)
2.二人で使うもので、今現役で遊んでいるもの
3.二人で使うもので、今は遊ばないけどとっておきたいもの
4.もういらないもの
おもちゃ棚のスペースが限られているのでここに置くものは
「二人で今現役で遊んでいるもの」だけを置くルールにしました。
1.それぞれ専用のスペースに移動
姉のものは姉の部屋に持っていきます。
妹のものは妹のリビング内の妹専用スペースに持っていきます。
ものを整理する力は自分専用スペースを管理することから。小さい子どもでも「自分専用スペース」を持つことはとても大切です。
2.今現役で二人で遊んでいるもの
そのままおもちゃ棚に残します。
これだけにすることで量がぐっと減るので片づけが楽になります。
3.今は使わないけど捨てたくないもの
子どもは自分でおもちゃを買うことができません。
大人からみれば「全然遊んでないしいらないんじゃあ」と思うものでも執着してしまいがち。
「なんでも捨てられちゃう!」ってお子様が感じたら、余計に執着がまします。
「捨てたくない!!」って気持ちを尊重してあげてください。
そして「ママが別の場所に置いておくから、遊びたくなったら言ってね」と別の場所(押入れの奥やクローゼットの上段等の不便な場所でOK」に保存してあげてくださいね。
半年、1年後にもう一度聞いてみると案外「もういらない」になっているかもしれません。
4. もういらないもの
これは簡単。寄付や譲る先があるものは差し上げて、ボロボロだな、と思ったらお子さんと一緒におもちゃに「ありがとう」といって処分。
寄付や譲る時の基準は「自分がもらったらうれしいか」です。
どちらも速やかに処理しないと半透明のゴミ袋を見てお子様が「やっぱりいる〜」となりますよ^^;
今回は3時間でこれだけのゴミになりました。

ステップ2 収納
さて分けたものを収納していきます。
ポイントはこれ
1アイテム 1引き出し(1カゴ)
おりがみの引き出しにはおりがみ(とおりがみと一緒に使うもの)
カードゲームにはカードゲーム
粘土のカゴには粘土
引き出しのなかがスカスカだとなんだか空間がもったいないような気がして、ついつい詰めたくなりますが、お子さんにちゃんと片づけて欲しければ
スカスカの余裕とわかりやすさ
子どもは大人より不器用なので放り込めば入る、くらいのゆったりさが必要。
またわかりにくい収納は「適当につっこんじゃえ」の片づけになります。
わからないことはやりたくない、大人だってそうですよね?
おもちゃ棚 Before

おもちゃ棚 After

見た目はさほど変わりませんが、このあと姉妹でラベリング。
引き出しもスカスカで「わかりやすい収納」になりました。
おもちゃ収納まとめ
1. 収納できる量を決める
持っているおもちゃ全てを収めようとすると、ぎゅうぎゅうになったりあふれたりでうまくいきません。
その収納棚に「片づけやすいように」収まるだけ収納します。
今回は「二人が現役で遊んでいるおもちゃ」と限定しました。
「あれもこれもここに置きたい!」とお子様がいうのであれば、
「じゃあどれか減らそうね」と量を決めることがとても大切です。
2. 「自分のもの」「自分のスペース」を明確に。
ものを管理する基本ってこれだと思うのです。
自分のもの、自分のスペースに責任を持つ。子どもの場合その一歩はおもちゃの片づけですよね。
つまりおもちゃだって「住所」を決めておかないと片づけがうまくいかないということなのです。



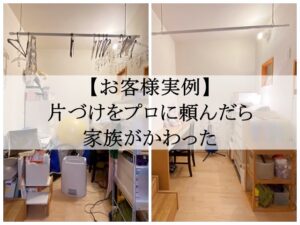


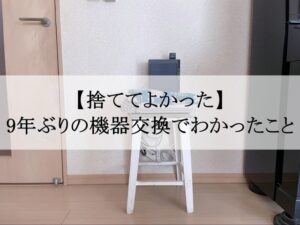


コメント